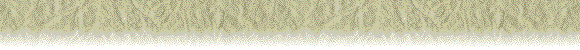 |
バイエルン国立歌劇場は私の最も好きな劇場だ。 何が好きかと聞かれると、「すべてが好き」と答えるしかない。 オペラ鑑賞の場合には開演前の気分の高まりがその日の公演に集中できるかどうかに多大な影響を及ぼす。 したがって開演時間まじかに息せき切って駆けつけるなど論外なのだ。 とは言うものの私もよくやってしまう。
この劇場に来場する人々はまず品が良い。 そして優雅だ。 またはたからみていても何とは無くゆったりしている。 これらの人々の中にいるだけで心にゆとりができ、オペラを見る準備ができてくるというものだ。
そして劇場自体の作りがすばらしい。 押さえの利いた豪華さがなんとも優雅だ。 地下のスナックにおいてある品々さえ上品だ。 したがって開演前、幕間も優雅な気分にどっぷりと浸ることができる。
演奏の質だが、これも文句なしに超一流だ。 私の訪れた世界各地約50のオペラ・ハウスの中での私の評価は群れを抜いた1位だ。 まず失望させられることは無い。
この演奏の質には聴衆の集中度が重要な影響を与えることはいうまでも無い。 ここは聴衆の質が実に高い。 オーケストラ、歌手、バレーそして裏方がその聴衆の期待に応える。 すばらしい相乗効果だ。 聴衆はその夜の演奏に満足すると惜しみなく拍手を送る。 これがまたすごく、えんえんと続く。 ミュンヒェンで演奏できる者の冥利ではないかと思う。 |
|
|
|
|
|
 国立歌劇場はマックス・ヨーゼフ・プラッツ Max-Joseph Platz に面して建つ。 上写真がその広場から撮ったもので、王宮=レジデンツ
Residenz はこの左側に位置する。 なおこの劇場のすぐ隣にはレジデンツテアター
Residenztheater と言う劇場がある。 ここは演劇用の劇場で、キュビリエ・テアター(別名アルテス・レジデンツテアター)ではないので注意を要する。 国立歌劇場はマックス・ヨーゼフ・プラッツ Max-Joseph Platz に面して建つ。 上写真がその広場から撮ったもので、王宮=レジデンツ
Residenz はこの左側に位置する。 なおこの劇場のすぐ隣にはレジデンツテアター
Residenztheater と言う劇場がある。 ここは演劇用の劇場で、キュビリエ・テアター(別名アルテス・レジデンツテアター)ではないので注意を要する。
ハウプトバーンホーフ(中央駅)方面からは19番のトラムが便利で、劇場前に止まる。 Sバーン、Uバーンだとマリエンプラッツ
Marienplatz から新市庁舎 Neues Rathaus の脇を北に200m余歩くとマックス・ヨーゼフ・プラッツだ。
入場券売り場はかつては写真右側のマキシミリアン・シュトラーセ Maximilianstraße
を劇場に沿って行った劇場裏手の搬入口のある道を渡った所にあったが、現在この場所は再開発中で、暫定的?に劇場正面を入った右側にある。
|
Münchner Festspiele 1971
|
| 1971年7月26日 R. シュトラウス 「サロメ」 |
| |
Salome |
Leonie Rysanek |
|
Jochanaan |
Dietrich Fischer-Dieskau |
| |
Herodias |
Astrid Varney |
|
Herodes |
Gerhard Stolze |
| |
Narraboth |
Wieslaw Ochman |
|
Erst. Nazarener |
Kurt Böhme |
| |
指揮 |
Ferdinand Leitner |
|
演出 |
Günther Rennert |
| |
美術 |
Rudolf Heinrich |
|
衣装 |
Rudorf Heinrich |
| 1971年7月27日 モーツアルト「魔笛」 |
| |
Tamino |
Adorf Dallapozza |
|
Pamina |
Edith Mathis |
| |
König |
Rita Shane |
|
Sarastro |
Franz Crass |
| |
Papageno |
Herman Prey |
|
Papagena |
Monique Lobasa |
| |
Monostatos |
Friedrich Lenz |
|
Sprecher |
Dietrich Fischer-Dieskau |
| |
指揮 |
Rudolf Kempe |
|
演出 |
Günther Rennert |
| |
美術 |
Josef Svoboda |
|
衣装 |
Erick Kondrak |
| 1971年7月28日 ヴェルディ「シモン・ボッカネグラ」 |
| |
Simon |
Eberhard Wächter |
|
Fiesco |
Ruggero Raimondi |
| |
Ameria |
Gundula Janowitz |
|
Gabriele |
Robert Ilosfalvy |
| |
Paolo |
William Murray |
|
Pietro |
Jánis Tessényi |
| |
指揮 |
Claudio Abbado |
|
演出 |
Otto Schenk |
| |
美術 |
Jürgen Rose |
|
衣装 |
Jürgen Rose |
| 1971年7月29日 モーツアルト「後宮からの逃走」 キュビリエテアター |
| |
Constanze |
Sylvia Geszty |
|
Belmonte |
Werner Hollweg |
| |
Blonde |
Elke Schary |
|
Pedrillo |
Willi Brokmeier |
| |
Osmin |
Zoltan Kelemen |
|
Selim |
Worfgang Schwarz |
| |
指揮 |
Heinrich Hollreiser |
|
演出 |
Günther Rennert |
| |
美術 |
Wilhelm Reinking |
|
衣装 |
Wilhelm Reinking |
| 1971年8月 1日 ベルク 「ヴォイツェック」 |
| |
Wozzeck |
Theo Adam |
|
Marie |
Wendy Fine |
| |
Hauptmann |
Georg Paskuda |
|
Doktor |
Kieth Engen |
| |
指揮 |
Carlos Kleiber |
|
演出 |
Günther Rennert |
| |
美術 |
Rudolf Heinrich |
|
衣装 |
Rudolf Heinrich |
| 1971年8月 6日 ヴァーグナー 「ニュルンベルクのマイスタージンガー」 |
| |
Walter |
Gerhard Unger |
|
Eva |
Leonore Kirschstein |
| |
Sacks |
Theo Adam |
|
Pogner |
Franz Crass |
| |
Beckmesser |
Klaus Hirte |
|
David |
Gerhard Unger |
| |
指揮 |
Ferdinand Leitner |
|
演出 |
Rudolf Hartmann |
| |
美術 |
Hermut Jürgens |
|
衣装 |
Sophia Schröck |
1971年当時わが国ではようやくバイロイトやザルツブルクのフェスティバルは愛好家の間に名前が知られてきていた。 それというのもこの年またはその前年あたりから夏の音楽祭めぐりのグループツアーが催されるようになり、音楽会会場でそのチラシが配られるようになったからだ。
私がこの年にヨーロッパに行くことにしたきっかけは、超格安の航空券(と言ってもロンドン往復で25万円、この時代には格安航空券は存在していなかったのだ。)が入手できることになったことと、アメックスからバイロイトの入場券が購入できることになったからだ。 そのアメックスからはさらにザルツブルクとミュンヒェンのフェスティバルのチケットの入手も可能だと言う連絡をもらった。 スケジュールを観るとミュンヒェンのフェスティバルの出し物、出演者はザルツブルクよりはるかに魅力的だ。 そこでミュンヒェンに重点を置くことにして6演目のチケットを購入した。
まず最初の日に観た「サロメ」にはまさに圧倒された。 あの軽いふわっとした感じのフィッシャー・ディースカウの声が、この日は全く違った響きを持っていたのだ。 自信に満ちたヨカナーンの声が、井戸の中から朗々と聞こえてき、私の体が大きく共振する。 「サロメ」の公演に接するたびに今でもこのときのディースカウの感動がよみがえってくる。 リザネックのサロメはイメージと大いにかけ離れていて興ざめであったが。
「魔笛」でのヘルマン・プライのパパゲーノ、「マイスタージンガー」のクラウス・ヒルテのベックメッサーなどの名演技名歌唱も大いに堪能したものだ。 |
|
1974 - 1976
|
| 1974年3月12日 R. シュトラウス 「エレクトラ」 |
| |
Elektra |
Danica Mastilovic |
|
Orest |
Franz Crass |
| |
Klytämnestra |
Astrid Varnay |
|
Aegisth |
Fritz Uhl |
| |
Chrisothemis |
Hildegard Hillebrecht |
|
junger Diener |
Georg Paskuda |
| |
指揮 |
Wolfgang Sawallish |
|
演出 |
Günther Rennert |
| |
美術 |
Rudolf Heinrich |
|
衣装 |
Rudorf Heinrich |
| 1974年3月14日 ヴェルディ 「ドン・カルロ」 |
| |
Carlos |
Robert Ilosflvy |
|
Elisabeth |
Anna Alexieva |
| |
Philipp II |
Karl Christian Kohn |
|
Rodorigo |
Wolfgang Brendel |
| |
Eboli |
Patricia Johnson |
|
Großinquisitor |
Victor von Halem |
| |
指揮 |
Rudolf Kempe |
|
演出 |
Günther Rennert |
| |
美術 |
Josef Svoboda |
|
衣装 |
Sophia Schröck |
| 1974年3月19日 ムソルグスキー 「ボリス・ゴドゥノフ」 |
| |
Boris |
Marti Talvela |
|
Schuiskij |
Fritz Uhl |
| |
Grigorij |
Toni Krämer |
|
Marina |
Eva Randova |
| |
Pimen |
Franz Crass |
|
Blõdsinniger |
Gerhard Stolze |
| |
指揮 |
Heinrich Bender |
|
演出 |
Hans Hartleb |
| |
美術 |
Hermut Jürgens |
|
衣装 |
Jürgen Rose |
| 1976年5月 6日 プッチーニ 「トスカ」 |
| |
Tosca |
Teresa Kubiak |
|
Cavaradossi |
Placido Domingo |
| |
Scalpia |
Shrrill Milnes |
|
Angelotti |
Raimund Grumbach |
| |
指揮 |
Jesus Lopez-Cobos |
|
演出 |
Götz Friedrich |
| |
美術 |
Rudolf Heinrich |
|
衣装 |
Reinhardt Heinrich |
| 1976年5月13日 モーツアルト 「魔笛」 |
| |
Tamino |
Werner Hollweg |
|
Pamina |
Erika Köth |
| |
König |
Hildegard Uhlmacher |
|
Sarastoro |
Franz Crass |
| |
Papagena |
Janet Perry |
|
Papageno |
Wolfgang Brendel |
| |
Monostatos |
Gerhard Unger |
|
Sprecher |
Lief Roar |
| |
指揮 |
Heinrich Bender |
|
演出 |
Günther Rennert |
| |
美術 |
Josef Svoboda |
|
衣装 |
Erich Kondrak |
この期間の公演についてはほとんど記憶が薄れてしまった。 「ボリス」が絢爛豪華、重厚な舞台であったこと、そして「トスカ」で初めて聞いたドミンゴがほとんど印象に残らなかったことくらいだろうか。 |
1999
|
| 1999年10月 8日 ロッシーニ 「アルジェリアのイタリア女」 |
| |
Isabella |
Maria José Trullu |
|
Lindoro |
Paul Gimenez |
| |
Elvira |
Simina Ivan |
|
Mustafa |
Lorenzo Regazzo |
| |
Taddeo |
Carlos Chausson |
|
Haly |
Gerhard Auger |
| |
指揮 |
Marcello Viotti |
|
演出 |
Jean Pierre Ponnelle |
| |
美術 |
Jean Pierre Ponnelle |
|
衣装 |
Jean Pierre Ponnelle |
この年は北イタリアのドロミテへのハイキング目的でヨーロッパに出向いたのだが、ボルツァーノに近いゲート・シティーと言うことでミュンヒェンを選んだ。 当然この地でのオペラも念頭に入れてのことだ。
インターネットでこの公演チケットを購入しようと試みたがすでに完売。 そこでアーベントカッセが開く30分ほど前から入り口に並ぶ。 すでに1人の日本人が並んでいた。 程なくチケットを持った人が現れ、私はその人からフェース・ヴァリューでチケットを手に入れることができた。
この演出・美術・衣装ジャン・ピエール・ポネルの「イタリア女」はまず衣装がコミカルかつ豪華絢爛、そして演出がこの音楽、衣装、美術に実にマッチしており、また照明も当を得たものであった。 歌手陣、オーケストラも文句無く、ミュンヒェンで見たオペラの中では一番私を楽しませ、満たされた気分にしてくれたオペラと言えよう。
2001年同じポネルの演出・美術・衣装でウイーン国立歌劇場でアグネス・バルツァのイザベッラで観たが雲泥の出来でこちらはほとんど楽しめなかった。 |
2001
|
| 2001年11月24日 ヘンデル 「エーシスとガラテア」 キュヴィリエテアター |
| |
Galatea |
Juliane Banse |
|
Acis |
Kobie van Rensburg |
| |
Damon |
Toby Spence |
|
Polyphemus |
Markus Marquardt |
| |
指揮 |
Joshua Rifkin |
|
演出 |
Stefan Tilch |
| |
美術 |
Antony McDonald |
|
衣装 |
Antony McDonald |
| 2001年11月24日 パーセル 「ディードーとエネアス」 キュヴィリエテアター |
| |
Dodo |
Anna Caterina Antonacci |
|
Aeneas |
Jon Ketilsson |
| |
Belinda |
Sophie Daneman |
|
Spilit |
Anja Augustin |
| |
指揮 |
Joshua Rifkin |
|
演出 |
Aron Stiehl |
| |
美術 |
Antony McDonald |
|
衣装 |
Antony McDonald |
| 2001年11月25日 ベッリーニ 「清教徒」 |
| |
Elvira |
Edita Gruberova |
|
Arturo |
Gregory Kunde |
| |
Riccardo |
Paolo Gavanelli |
|
Giorgio |
Alastair Miles |
| |
Valton |
Gerhard Auger |
|
Enrichetta |
Liliana Mattei |
| |
指揮 |
Friedrich Haider |
|
演出 |
Jonathan Miller |
| |
美術 |
Isabella Bywater |
|
衣装 |
Clare Mitchell |
| 2001年11月26日 ベルリオーズ 「トロイア人」 |
| |
Énée |
John Villars |
|
Didon |
Waltraud Meier |
| |
Cassandre |
Deborah Polaski |
|
Chorébe |
Gino Quilico |
| |
Andromache |
Mirjam Baßler |
|
Anna |
Hélène Perraquin |
| |
Ascagne |
Stella Doufexis |
|
Narbal |
Jan-Hendrick Rootering |
| |
指揮 |
Zubin Mehta |
|
演出 |
Graham Vick |
| |
美術 |
Tobias Hoheisel |
|
衣装 |
Tobias Hoheisel |
この年は久しぶりにオペラ鑑賞を目的に、ヨーロッパ各地のスケジュールを見比べながら旅程を作成した。 その結果、ミュンヒェンで3夜(4公演)、ウィーンで3公演、初めて訪れるプラハで1公演を見るということになった。 特にミュンヒェンではかねてより一度観ておきたいと思っていた「トロイア人」と4月にニューヨーク・シティー・オペラで初めて観てほほえましく思った「エーシスとガラテア」が組み込めた。 おまけに「エーシス」は再び訪れたいと思っていたキュビリエ・テアターでの公演である。 ただしこの公演のチケットは完売であった。
「エーシス」についてはキュビリエ・テアターの項で述べることにして、「清教徒」に話を移そう。 ベッリーニ作品は余り観たことがなく、この作品についてはかなり以前に藤原歌劇団の公演で観たような気がするがそのパンフレットが見当たらないので観たことがないのかもしれない。 不思議なのだがベッリーニの公演を見つけると観たくなるのだ。 しかし今回は「トロイア人」とキュビリエ・テアターに心を奪われていて、この作品はまあ観ておこうかといった感じでチケットを購入した。 ところがエディタ・グルベローヴァの完璧な歌唱により実に密度の濃い公演に酔いしれた。 幕が下りると嵐のような賞賛の拍手に包まれ、いつ果てるともなくそれが続く。 これがミュンヒェンの聴衆だ。
「トロイア人」はメットのレヴァインのLDで十分予習して行った。 第1幕の落城間近のトロイのセットはなかなか良く、これは楽しめそうだとひざを乗り出したが、第2幕目はがらっと趣が変わり、カルタゴ人の服装が何と中国の国民服のようなもので一気にイメージが壊れた。 そのせいか演奏まで精彩を欠いたものに感じられたのは残念だった。 オペラとはまさに総合芸術である。 |
|
2002-2003 シーズンのオペラのチケットは特別公演のカテゴリーSの場合だと最高240ユーロだが、通常公演はおおむねカテゴリーH(最高85ユーロ)、I(最高97ユーロ)がが多い。 「清教徒」や「ラインの黄金」はカテゴリーK(最高129ユーロ)、「神々のたそがれ」がL(最高160ユーロ)、大晦日の「こうもり」がM(最高190ユーロ)と良心的だ。
チケットはバイエルン国立歌劇場のホーム・ページ http://www.bayerische.staatsoper.de/ から席まで指定できる。
|
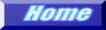  |
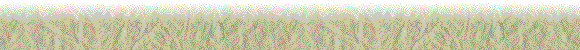 |
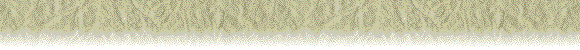
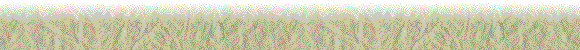
 国立歌劇場はマックス・ヨーゼフ・プラッツ Max-Joseph Platz に面して建つ。 上写真がその広場から撮ったもので、王宮=レジデンツ
Residenz はこの左側に位置する。 なおこの劇場のすぐ隣にはレジデンツテアター
Residenztheater と言う劇場がある。 ここは演劇用の劇場で、キュビリエ・テアター(別名アルテス・レジデンツテアター)ではないので注意を要する。
国立歌劇場はマックス・ヨーゼフ・プラッツ Max-Joseph Platz に面して建つ。 上写真がその広場から撮ったもので、王宮=レジデンツ
Residenz はこの左側に位置する。 なおこの劇場のすぐ隣にはレジデンツテアター
Residenztheater と言う劇場がある。 ここは演劇用の劇場で、キュビリエ・テアター(別名アルテス・レジデンツテアター)ではないので注意を要する。